子どもが不登校になるのは、保護者にとって大きなチャンスだと思った一本の電話

「どうしても聞いて欲しいことがあるんです」と、保護者さんからメールがきた。
夜、21時過ぎまで授業をしている僕は、夕方頃に仕事が終わる保護者さんと入れ違う形になってしまい、なかなか電話を受けることができなかった。
「遅くにお電話してもよろしいでしょうか?」
大丈夫と伝え、授業が終わって帰り道を歩いていたとき。
電話がかかってきた。
時間は、22時を過ぎていた。
まさか、その電話が想定外の喜びをもたらしてくれようとは、全く考えていなかった。
その保護者さんに初めてお会いしたとき、とても辛そうにお子さんの話をしていた。
学校へ行けないこと。
子どもが、人の目を気にしていること。
進学が心配なこと。
母親として、すごく不安なこと。
「どうしたらいいかわからないんです……」
滋賀県の教育委員会主催でおこなった講演で僕の話を聞き、「この人ならっ!」と思って、連絡をくださったらしい。
まさに、ワラにもすがる思いで僕たちを頼ってくれた。
まずは、家からも出られない状態だったので、ご自宅まで行って生徒面談をおこなう。
今の自分をどう思っているか。
どうしたいのか。
じっくり話を聞いて、今後の戦略を立てる。
しばらくすると、中学生の彼は、順調に変化していった。
しかし、保護者さんはずっと不安を抱えていた。
「全然、勉強しないんです……」
「ゲームばかりしているのです……」
一番身近で、子どものことを見ているのだから、心配に思う気持ちは痛いほどわかる。
他の子どもたちは、日中は学校へ通っている。
しかし、我が子を見ていると、昼間も家にいて、ダラダラしているように見える。
このままで大丈夫?
ほんとに変わっているの?
不安に思わないほうが不思議だ。
僕は、変化したポイントや見るべきポイントを逐一、伝えていった。
家での表情は、以前と比べてどうですか?
会話の量、増えていますか?
言葉、変わっていませんか?
すると……
「あっ、そう言えば、前よりも表情が柔らかくなった気がします。
よくしゃべるようになりましたし、“ 〜したい”って言うようになりました」
それを聞いて、僕は説明を加える。
ですよね?
それが、成長です。
勉強しない。
ダラダラしている。
ゲームばかりしている。
目の前にある行動だけを見たら、全然変わっていないように思うかもしれません。
でもね。
行動が変わる前には、意識が変わります。
だから、言葉が変わるし、表情も変わっている。
彼、すごく、前向きに変化していますよ。
こうやって、僕は子どもの成長を、保護者さんに伝えていった。
どこが変化しているかを詳しく伝えていった。
我が子が不登校になると、どんな親でも不安になる。心配になる。
想像できないくらいの苦しみが、そこにはあるだろう。
世間からの目。
子どもの将来への不安。
ゴールが見えない日々。
答えが見えず、必死でもがく。
子どもが不登校になり、心を病んでしまう保護者のかたも少なくない。
不登校は、長期戦になることが多い。
学校へ行けることもあれば、行けないこともある。
一進一退を繰り返す。
カウンセリングやフリースクールへ行っても、何度かすると「行きたくない」と言う。
打つ手が見つからず、途方にくれる。
僕なんかがわからないくらいに、苦しいだろう。
だから、僕は保護者のかたに声をかける。
「どんな小さなことでもいいです。
不安があれば、どんなときでも言ってください。
いつでも聞くので!」
不登校の問題は、チーム戦だと思っている。
いくら子どもだけがガンバっても意味がない。
保護者の人が力んだところで、子どもがついてこなければなにも変わらない。
子ども本人と保護者、そして関わる大人たち。
一体となって取り組むことで、不登校の課題に立ちむかうことができる。
電話をくださった保護者さんは、はじめのうちは、とにかく力んでいた。
「自分がなんとかしないと……」という気持ちが強くあった。
気負ってしまい、しんどくなっていた。
しかし、子どもが前向きになっていくことで、保護者さん自身も変わっていったのだと言う。
「自分の子どもを信じられるようになってきたんです。
今までは、“信じている”って言っていたけれど、どこかウソっぽかったのかも知れません。
今は、“大丈夫”って心から思えるのです」
そして、彼女は言った。
「もうね、そちらへ通うことになって、目に見えるほど変わってきたんです。
今までは、学校へ行けない理由を聞いてもなにも言いませんでした。
でも、最近は話してくれるんです。
実はこう思ってるねんって」
僕は、嬉しいなぁと思いながら、バス停のベンチに腰掛けて話を聞いていた。
「みんな幸せになっています。子どもも私も家族も。
ほんと良かった。
あと、自分でも気が付いていなかったのですが、私自身の言葉が変わってきたらしいのです。
発する言葉に説得力が増したみたいなんです」
話を聞いていて、僕は思わず、はっとした。
今まで、疑問に思っていたことが解けたのだ。
僕が今までお会いした不登校の保護者さんや不登校だった子を育てた人たちはみんな、とても強い人だった。
でも、違う。
“強い”のではなく、“強くなった”のだ。
不登校という課題にぶつかり、ぼろぼろになりながらも、子どもと一緒に闘ってきたのだ。
そして、その過程を通して、保護者自身も成長し、強くなっていったのだろう。
我が子が不登校になったら、きっと途方に暮れてしまう。
「どうして……」
どうしたらいいかもわからないし、不安になる。
育て方が間違っていたのか?
なにか問題があったのだろうか?
「ツイていないな……」
なんて、思うかも知れない。
「どうして、私だけがこんなしんどい思いをしないといけないのか?」と、不運を呪いたくなることもあるだろう。
でも、もしかしたら、不登校というのは、子どもがくれた“保護者が成長するための機会”なのかも知れないと、僕は思うのだ。
不登校になっていなければ、自分の子育てと真正面から向き合うことはない。
血を吐くような苦しさも感じていないだろう。
しかし、不登校になったからこそ、向き合うことができる。
子どものことについて深く、深く、考えることができる。
「今までは、子どもに“知っている”ことを話していました。
でも、それじゃあ伝わらないんですよね。
今、私は心から感じたことを話すことにしています。
そうすると、ちゃんと届くんですよ。言葉が。」
「私、自分自身がすごく変わった気がします」
僕は、嬉しい報告のお礼を伝え、電話を終えた。
大学生のとき、瀬戸内寂聴さんは、僕に言ってくれた。
「辛いこと、しんどいことを経験した人ほど、人に優しくできるんですよ」
きっと、不登校の保護者さんも同じだ。
しんどい経験を通したからこそ、しなやかで、芯が強い人になったんだ。
不登校の問題は、とてもしんどい。
でも、その先に、大きな喜びや成長があるのならば、僕たちは、歯を食いしばりながらも、笑って不登校という課題に取り組んでいけるのかも知れない。

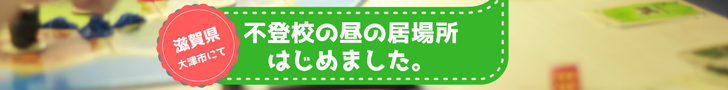





![[講演音声]不登校の一問一答 in 前橋](http://www.blog.dlive.jp/wp-content/uploads/2018/10/39786160_265081104112207_4795976760086757376_n-150x150.jpg)

























